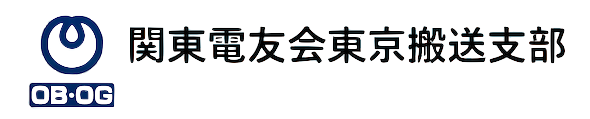「鎌倉の古刹が建つゴールデンルートを散策し、繁栄した源氏・北条の往時を偲びませんか」
総武地域懇談会で鎌倉ハイキングを計画しました。鶴岡八幡宮、ドラマ「鎌倉殿13人」が執権、創基した寺院等をまわります。
神奈川をはじめ、他の地域懇談会の方の参加も大歓迎です。多数の参加をお待ちします。
【ポイント】
鎌倉幕府150年で執権(将軍)は9人、なぜか源氏執権は33年3人、幕府は北条(妻政子の存在)が采配した。現存の寺院等の開基は北条執権の時代に建っている。
1. 実施日
5月30日(金) 予備日6月6日(金)
2. 行程の概要
JR北鎌倉駅~円覚寺(鎌倉随一の国宝建築が残る寺)~明月院(別名アジサイ寺、花ショウブと百花繚乱)~建長寺(禅宗の専門道場(寺院内のほとんどが重要文化財)~鶴岡八幡宮(鎌倉武士の守護神、勝運、出世運としてパワースポット)~お疲れ昼食会~鎌倉駅で解散。徒歩行程7Km、緩い下り坂道です。
3. 集合場所・時間
JR北鎌倉駅・駅前広場 10時40分集合
4.参加申込み〆切
5月20日(火)
幹事までメール、電話(伝言も可)
・メール:ishida.k@nifty.com
・電 話:080-1983-0043
※注意事項等
1.遅い昼食になりますので、携行食持参ねがいます。
2.雨天等で順延の場合は、電話連絡します。
3.大河ドラマ(2022)「鎌倉殿の13人」を思い浮かべながら散策するのも一興。
【参考】
1.鎌倉幕府
鎌倉幕府は、1185年(文治元年)に源頼朝によって開かれ、1333年(元弘3年)に滅亡しました。約150年の歴史でした。
これまで朝廷が政治を行っていた時代から、武士が実権を握る時代へと変わる大きなきっかけを作りました。戦いに勝ち、政治の仕組みを整え、そして鎌倉に新しい幕府を開いた。
頼朝から始まった鎌倉幕府ですが、源氏将軍は第3代の源実朝(みなもとのさねとも)が暗殺されて途絶えます。とはいえ、ここで鎌倉時代は終わりません。
将軍に関しては、第4~5代は公家最高位の摂家(せっけ)から、第6代以降は皇族からふさわしい人を就任させていました。それぞれ摂家将軍、宮将軍(みやしょうぐん)と呼ばれ、鎌倉幕府の将軍は9代まで続きます。
実は、3代で終わった源氏より、源氏ではない将軍のほうが多かったのです。
鎌倉時代の将軍9代のうち、源氏はなんと1~3代だけ!
ただし、幕府を実際に支配していたのは、頼朝の正室・北条政子(ほうじょうまさこ)の実家にあたる北条氏でした。
頼朝存命時の幕府は、将軍独裁体制でした。しかし、彼が急死してから、将軍に仕える御家人(ごけにん)の力が強くなります。
第2代将軍の源頼家(みなもとのよりいえ)は、18歳の若さで跡を継ぎましたが、補佐が必要な状態でした。そこで有力な御家人たち13人での合議制がとられるようになりました。この13人の中心にいたのが、北条氏です。
鎌倉時代は、有力な御家人同士の激しい戦いがたびたび発生しました。
他の御家人たちが滅んでいくなか、北条氏は事実上の最高責任者にあたる執権(しっけん)をはじめ、幕府の要職を独占するようになります。
2.円覚寺
円覚寺(えんがくじ)は、神奈川県鎌倉市にある臨済宗の寺院で、鎌倉五山(格式の事)の第二位に位置する名刹です。鎌倉幕府8代執権の北条時宗が、中国の僧侶無学祖元を招いて建立しました。
円覚寺の伽藍は、鎌倉独特の谷戸(やと)と呼ばれる丘陵地が浸食されて出来た谷に沿って建てられています。三門を入り、仏殿、方丈へと徐々に登っていく配置は、この土地の高低差を生かした壮大な空間をつくりだしています。
鎌倉時代後期に建立され、国宝の舎利殿や梵鐘など貴重な建築物が残る。
1301年、9代執権の北條定時の時代に造られた鎌倉三名鐘の一つです。鎌倉で一番大きい梵鐘でもあり、国宝に指定されています。
円覚寺は、禅の教えを人々に広め、国の平安を守り、蒙古襲来による犠牲者を弔うために建立されたといわれています。
3.明月院
紫陽花の名所として知られ、あじさい寺としても知られている。
ブルーが美しい明月院の紫陽花の参道。
その開花時期は、毎年5月下旬~7月上旬。
この季節の明月院は、平日でも非常な混雑で、行列が絶えません。
本堂の奥には、有名な円窓「悟りの窓」があり、その向こう側に広がる
後庭園の紅葉を見ることができます。「悟りの窓」は禅や円通の心を表しているそうです。
5代執権「北条時頼」の墓所が境内にある
4.建長寺
禅によって国の振興をはかる為、時の5代執権「北条時頼」が中国(宋)の高僧蘭渓道隆を迎えて創建した日本最初の禅宗専門道場で幕府と強く結び付きました。
日本で最初の禅の(専門)道場である。
建築は、総門、三門、仏殿、法堂、方丈が一直線に連なる禅宗様式である。
また、建築物はほとんどが重要文化財指定であり、法堂の釈迦苦行像と天井の雲竜画は有名である。
鎌倉五山(格式の事)の第一位に位置する名刹です。
鎌倉時代の末には、寺のお坊さんその他の人数は約千人に近い数であったといわれ、また、野菜や豆腐入りのけんちん汁(建長汁)はここが発祥といわれている。
5.鶴岡八幡宮
鶴岡八幡宮は、鎌倉幕府を築いた源頼朝(みなもとのよりとも)公とゆかりの深い神社です。 鶴岡八幡宮の歴史は、源頼朝公の祖先・源頼義(みなもとのよりよし)が、由比ガ浜に源氏の氏神として八幡神を祀ったことからはじまります。 その後、1180年に源頼朝公が現在の場所に遷して、現在の鶴岡八幡宮の基礎が造られました。
鶴岡八幡宮が有名な理由
源氏の氏神として信奉され、鎌倉武士の守護神とされていました。
源頼朝にあやかって勝運・出世運にご利益のあるパワースポットとして知られている。
厄除け・健康・心願成就、縁結びなどのご利益があり、境内にはパワースポットが数多く存在します。